※当ブログは、アフィリエイトプログラムを利用しています。
年末年始のおせち、何買うか迷っていませんか?この記事では準備の順番、冷凍できるもの・冷蔵するものの見分け方、最後までおいしく食べる方法をやさしく解説します。
この記事のポイント
・必要量の決め方(人数別)
・冷凍できるものと冷蔵するものの見分け方
・年末の買い物スケジュールと冷凍庫対策
・残りおせちのリメイクと食べ切り術
それでは早速見ていきましょう。
年末年始の営業短縮で慌てない!「おせち何買う」早見リストと優先順位
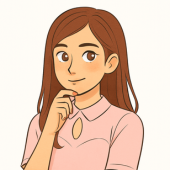
年末にいつも買い忘れが出てしまって慌てます。どれを先に買えば安心ですか?
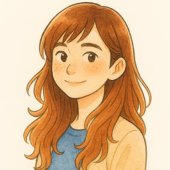
買う順番ひとつで余裕が生まれますよ。次の節では、優先順位のつけ方と家族に合わせた早見リストをわかりやすく紹介します。
年末が近づくと、スーパーやデパートの営業時間が短くなり、買い物の計画を立てるのがむずかしくなります。おせち料理の準備も同じで、「何を買えばいいの?」と迷っているうちに売り切れてしまうこともあります。この記事では、家族の人数や好みに合わせて「おせち何買う?」をスムーズに決められる早見リストと、優先して買うべきものの順番を紹介します。あわただしい年末でも慌てず、落ち着いて準備を進められるようにしましょう。
年末年始の営業時間を見越した買い出しタイミングの決め方(急がないコツ)
年末になると、多くのお店が営業時間を短縮したり、休業に入ったりします。そのため、買い出しのタイミングを早めに決めておくことが大切です。おすすめは、冷凍保存できるおせちや食材から先に購入しておくことです。たとえば、冷凍黒豆や数の子などは早めに買っても品質を保てます。生鮮食品は日持ちが短いので、年末直前に少量を買うとムダがありません。焦らず、買う順番を「冷凍できるもの→日持ちするもの→生もの」の順にするとスムーズです。
家族人数別「おせち何買う」目安表(冷凍・冷蔵の分量つき)
家族の人数によって必要なおせちの量は大きく変わります。2~3人なら1~2段のおせちがちょうどよく、4人以上なら3段タイプや、単品おかずを組み合わせるのがおすすめです。冷凍おせちは余っても保存できるので、少し多めに買っても安心です。一方で、冷蔵タイプは食べきれる分だけを選ぶのがコツ。特に子どもがいる家庭では、好きな料理を中心に選ぶと残りにくくなります。分量を決めてから買うことで、食材ロスも防げます。
| 家族人数 | 重箱の目安 | 主な品目例(量の目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1〜2人 | 1段(小) | 黒豆 100〜150g、栗きんとん 100g、かまぼこ 1本分相当 | 少量パックや単品を組合せるとムダが少ない |
| 2〜3人 | 1〜2段 | 黒豆 150〜200g、煮しめ 300〜400g、伊達巻 1本 | 冷凍保存できる品を1〜2品入れると安心 |
| 4人 | 3段(小〜中) | 黒豆 200〜300g、数の子 150〜200g、煮しめ 400〜600g | 家族構成で好みを優先しつつ量を調整 |
| 5〜6人 | 3段(中〜大) | 各種おかずを増量(煮物600g〜、伊達巻2本など) | 余りが心配なら冷凍保存前提で少し多めに購入 |
| 7人以上 | 3段〜複数 | 大皿+単品追加で対応 | 来客用は単品で追加購入すると調整しやすい |
通販と近所スーパー、どちらで買う?年末年始に合った買い方の選び方
おせちは通販とスーパーどちらでも購入できますが、それぞれにメリットがあります。通販は早期予約で割引や特典があることが多く、重たい荷物を運ばなくていいのが便利です。一方、スーパーでは実物を見て選べる安心感があります。年末年始の忙しい時期には、冷凍おせちは通販で、鮮度が大事な食材はスーパーで買う「ハイブリッド買い」が効率的です。両方の良さを上手に使い分けると、無理なく準備が進みます。
おせちの冷凍できるもの・冷蔵するものを理解して保存を賢くする方法
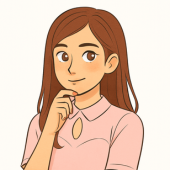
冷凍しても大丈夫なものと冷蔵が向くものの見分け方がよくわかりません。失敗したくないです。
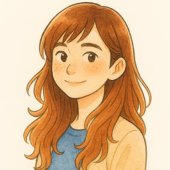
保存方法を誤ると味や食感が落ちてしまいます。これから、品目別に冷凍・冷蔵の適性と具体的な保存のコツを順に解説します。
おせちは保存方法を正しく知っておくことで、味を長く保てます。冷凍できる料理と冷蔵のほうが良い料理を区別しておくと、作り置きや通販おせちの保存にも役立ちます。ここでは、代表的なおせちの保存方法と、風味を保つコツをわかりやすく解説します。
冷凍保存OKなおせち一覧と保存期間の目安(品質を守るポイント)
冷凍できるおせちは、黒豆、田作り、伊達巻、海老のうま煮などが代表的です。これらは冷凍しても食感や味が変わりにくく、1〜2週間ほど保存できます。冷凍時は空気を抜いて密封することが大切です。また、できるだけ平らに広げて冷凍すると、ムラなく凍ります。解凍の際は冷蔵庫でゆっくり戻すことで、味の劣化を防げます。冷凍庫の整理をしてから保存スペースを確保しておくと安心です。
| 品目 | 保存方法の目安 | 保存期間の目安(目安) | 保存時のポイント |
|---|---|---|---|
| 黒豆 | 冷凍可(加熱済み) | 冷蔵:2〜4日、冷凍:〜1か月 | 密封し空気を抜く、平らに冷凍 |
| 栗きんとん | 冷凍可(甘味が強い) | 冷蔵:2〜3日、冷凍:〜1か月 | 小分けして冷凍、解凍は冷蔵でゆっくり |
| 煮しめ(根菜) | 冷凍可(食感はやや変化) | 冷蔵:2〜3日、冷凍:2〜4週間 | 冷凍前に汁気を切り、密封保存 |
| 田作り(ごまめ) | 冷凍可 | 冷蔵:4〜5日、冷凍:〜1か月 | 乾燥しないよう密封。味が濃いものは日持ちしやすい |
| かまぼこ | 冷蔵推奨 | 冷蔵:5〜7日(未開封目安) | 開封後は早めに消費、冷凍は食感注意 |
| 紅白なます | 冷凍可(酢漬け) | 冷蔵:3〜4日、冷凍:2〜4週間 | 漬け汁ごと密封して冷凍、繊維の変化に注意 |
| 魚介系(海老など) | 冷凍可(調理済み推奨) | 冷蔵:1〜2日、冷凍:〜1か月 | 新鮮なうちに調理し冷凍。解凍は冷蔵庫で |
冷蔵が向く料理と傷みにくくする保存のコツ
冷蔵保存に向いているのは、かまぼこ、なます、煮しめなどです。これらは水分が多いため、冷凍すると食感が変わりやすいです。保存する際は、清潔な容器に入れて、汁気を少し切っておくと傷みにくくなります。また、冷蔵庫の奥よりも温度が安定した場所に置くと良い状態を保ちやすいです。翌日以降に食べる分はラップを二重にして乾燥を防ぐと風味が長持ちします。
解凍・再加熱の正しい手順で風味を損なわない方法
冷凍したおせちは、急に温めると味が落ちる原因になります。冷蔵庫で半日ほどかけてゆっくり解凍するのがポイントです。電子レンジを使う場合は、ラップをふんわりかけて中火で短時間ずつ温めると良いです。汁物は鍋で弱火にかけて温め直すと風味が戻りやすくなります。再加熱のしすぎは水分を飛ばすので注意しましょう。少し手をかけるだけで、できたてのようなおいしさが楽しめます。
「おせち 最後までおいしく食べる方法」プロ直伝のリメイク&再活用テクニック
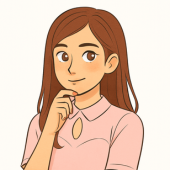
毎年残りがちで困っています。おいしく最後まで食べる工夫ってありますか?
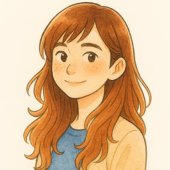
残りをそのままにしない工夫がいくつもありますよ。続く部分で、品目別の簡単リメイク法を実例とともにご紹介します。
おせちは三が日で食べきるのが理想ですが、どうしても残ってしまうことがあります。そんなときは、リメイクして新しい料理に変えるのがおすすめです。ここでは、おせちを最後までおいしく楽しむためのリメイク方法や、簡単にできるアレンジを紹介します。
黒豆・栗きんとん・煮しめ…品目別の簡単リメイクレシピ集
黒豆はホットケーキミックスに混ぜて蒸しパンにしたり、栗きんとんはトーストに塗るとスイーツ風に変わります。煮しめは炊き込みご飯にしても絶品です。残った田作りは砕いてごま和えのトッピングに使うと香ばしくなります。おせちは甘辛い味付けが多いので、洋風や中華風に変えると飽きずに食べられます。残り物をムダにせず、新しい味に出会える楽しみもあります。
味が濃くなったおせちの調整術と失敗しないアレンジ法
時間が経つと、おせちは味が濃く感じられることがあります。その場合は、野菜やごはん、豆腐など、味の薄い食材を組み合わせるとバランスがとれます。たとえば、煮物はスープにしてのばすと食べやすくなります。甘いおせちはヨーグルトに混ぜてデザート風にしても美味しいです。味を変えることで、最後までおいしく食べきることができます。
余りを短時間で一皿に変える時短アイデア(朝食・お弁当アレンジ)
忙しい朝でもすぐできるアレンジとして、残ったおせちをおにぎりの具やサンドイッチにするのがおすすめです。栗きんとんをパンに塗ったり、伊達巻を薄く切ってお弁当のおかずにすれば彩りもきれいです。少量ずつ残ったものも、少し工夫すれば立派な一品に変わります。手軽に食卓を整えたいときにぴったりです。
🔍家族みんなで楽しめるボリュームおせちなら↓
【匠本舗】どんどん売れる<料亭おせち>最近増えている“年末年始の営業短縮”に要注意!今のうちにできる食材準備のコツ
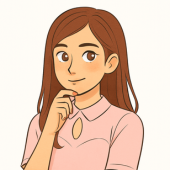
今年はお店が早く閉まると聞いて不安です。事前に何を準備すれば良いですか?
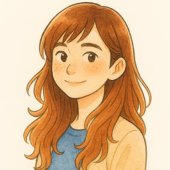
営業時間の変化に備えるには、計画とストックが鍵になります。次では、買い物スケジュールと“助かる食材”リストを具体的に示します。
近年、年末年始に休業や短縮営業をするスーパーや飲食店が増えています。そのため、「買い物ができない」「おせちが間に合わない」と焦るケースも増えています。この記事では、営業短縮が進む背景を知り、事前に準備しておくことで年末を安心して迎えるコツを紹介します。早めの行動が、ゆとりあるお正月を作る第一歩です。
なぜ年末年始の営業短縮が増えているの?背景と今後の傾向
営業短縮が増えているのは、人手不足や働き方改革による影響が大きいとされています。特に小売業では「従業員に休みをしっかり取ってもらう」動きが広がっており、年末年始は数日間の休業を設けるお店もあります。この流れは今後も続くと見られるため、利用者側も「いつ買うか」を意識して行動することが必要です。計画的に買い物を進めることで、慌てることなく年越しを迎えられます。
営業短縮の影響を受けないための買い物スケジュールの立て方
まずは、自分がよく利用するスーパーや通販サイトの営業スケジュールをチェックしておきましょう。冷凍や日持ちする食材から先に購入し、直前にしか買えない生鮮食品は最小限にします。冷凍庫の空きを確保しておけば、年末直前の混雑を避けながらも安心です。買い物リストを作って、いつ何を買うか決めておくと計画的に動けます。
休業期間中も安心!買っておくと便利な“助かり食材”リスト
年末年始に重宝するのは、調理いらずで保存も効く食材です。たとえば、冷凍うどんやレトルトスープ、冷凍野菜、焼きおにぎりなどはお正月中も手軽に使えます。おせちの合間に軽く食べられるものをストックしておくと、飽きずに食卓を楽しめます。食材を買うときは「冷凍・冷蔵・常温」のバランスを意識することが、賢い年末準備のコツです。
| 買うタイミング | 優先して買うもの(例) | 目的・理由 |
|---|---|---|
| 早め(余裕がある期間) | 冷凍保存できるおせち、冷凍野菜、レトルト、長期保存の調味料 | 品切れ対策・冷凍庫に入れておけるため混雑回避 |
| 中期(準備を始める時期) | 缶詰、乾物、乾麺、保存のきく副菜 | すぐ使える保存食として役立つ |
| 直前(直前の数日) | 生鮮(刺身、魚介類、鮮魚)、かまぼこ、なます用の野菜 | 鮮度重視の品は最後に調達して新鮮さを保つ |
| 当日・前日 | お酒・飲料、焼き物(買替え分)、すぐに食べる軽食 | 当日に必要な消耗品や最終調整用 |
年末に賢く準備して、ゆっくりお正月を迎えよう
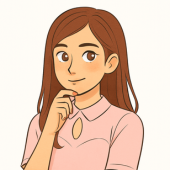
冷凍庫の空きが足りないことに気づかず困った経験があります。どんな整理が効率的ですか?
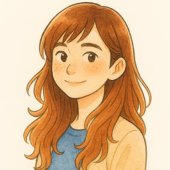
冷蔵庫・冷凍庫の整理は意外と効果大です。これから、実践しやすい収納テクや前倒しでできる下準備の方法を順に説明します。
お正月をゆっくり過ごすためには、年末のうちに“準備の段取り”を整えておくことが大切です。ここでは、冷蔵庫の整理や調理スケジュールの立て方など、忙しい時期でも無理なくできる工夫を紹介します。少しの工夫で、お正月の快適さがぐっと変わります。
冷蔵庫・冷凍庫の整理で“入らない問題”を防ぐ準備テク
おせちを買ったあと、「冷蔵庫に入らない!」と慌てる人は少なくありません。年末前に一度、冷蔵庫と冷凍庫の中身を整理しておきましょう。使いかけの調味料や冷凍食品を片付け、空きスペースを確保することで、おせちの保管もスムーズになります。冷凍庫は立てて収納できる保存容器を使うと、スペースを有効活用できます。
🧊「おせちを注文したいけど冷凍庫がいっぱい…」という方は、短期間だけ使えるフリーザーレンタルが便利。大容量冷凍庫を借りれば、年末のストレスも減ります。
【冷凍庫レンタル.com】▶ 家族の人数や来客予定から、ぴったりのおせちの数を決めたい方はこちら
→ 『おせちは何個買う?人数別・種類別の選び方ガイド』を読む
作り置き・下準備で当日の負担を減らす方法
年末は料理や掃除などやることが多いですが、少しずつ作り置きを進めると気持ちに余裕が生まれます。煮物や黒豆などは数日前に作っても味がなじんで美味しくなります。下ごしらえを済ませて冷凍しておくと、当日は温めるだけで一品完成。無理をせず、自分のペースで準備することが理想です。
忙しい年末でもできる“おせち+普段ごはん”の両立術
おせち作りだけでなく、普段の食事も大切です。おせちの材料を少し多めに買っておけば、年明けのご飯づくりがラクになります。たとえば、煮しめ用の根菜を多めに下ごしらえしておき、翌週の味噌汁や煮物に使うのもおすすめ。無駄を減らしながら、年明けも安心して過ごせます。家族みんなで協力して、楽しく準備を進めましょう。
まとめ
この記事で示した準備と保存・リメイクのコツを実行すれば、年末年始の営業短縮で買い物が難しくても慌てずに、おいしいお正月を落ち着いて迎えられます。以下の要点を押さえれば計画的に準備が進むはずです。
・買い物の順番は「冷凍できるもの→日持ちするもの→生もの」で決める
・家族人数に合わせて段数や量を目安にする
・冷凍保存が効くおせち(栗きんとん、煮物、田作りなど)を優先確保する
・冷蔵向きの品(なます、かまぼこ等)は直前購入で鮮度を保つ
・冷凍は密封して平らに置き、空気を遮断して保存期間を延ばす
・解凍は冷蔵庫でゆっくり行い、風味低下を防ぐ
・再加熱は短時間で行い、水分を飛ばさない工夫をする
・余ったおせちは炊き込みご飯やスイーツにリメイクして無駄を減らす
・冷凍庫の空き確保や保存容器の準備を事前に済ませる
・買い物リストとスケジュールで年末の混雑を回避する
早めに行動すれば、余裕あるお正月が待っています。
【匠本舗】どんどん売れる<料亭おせち>

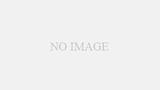
コメント